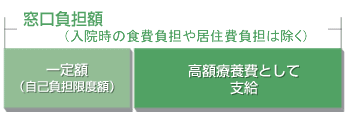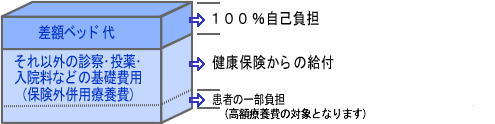また、住民税非課税者については標準負担額の減免制度があります(事前に健保組合の承認が必要です)。なお、被保険者が負担する標準負担額は高額療養費の対象になりません。
予備知識
・「入院時食事療養費」→保険者が直接医療機関に支払う。
・「食事療養標準負担額」→患者が全額支払う。
「入院中の食費に保険が使える」と言っているサイトは入院時食事療養費のことを言っているのであり、「入院中の食費に保険使えない」と言っているサイトは、標準負担額のことを言っている。
適用区分Cの限度額適用認定証は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」と書いてあるが、この「標準負担額」というのが、「自己負担する必要のある食費」のことです。
食事「療養」費と呼ぶことから考えて、食事も入院中の医療行為(治癒行為)の一環という考え方です。
標準負担額の減額を申請するとき(低所得者が入院したとき)
被保険者が住民税非課税者である場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し、申請が承認されれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証とともに医療機関の窓口に提示すれば標準負担額が1食につき210 円に減額されます。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方で過去12 ヶ月の入院日数が91 日以上となった場合には、再度申請手続を行なうことにより長期入院該当者として標準負担額が1食につき160 円に減額されます。
*協会けんぽや国民健康保険の場合、住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超える場合、入院時食事療養費の自己負担額が安くなります。この場合は、過去1年間に90日の入院日数があれば、良いことになります。但し、健康保険組合の場合は、「長期入院91日目以降」という形で別に独自の規約を設けて運営しているところもあります。この場合は、同一病院で90日以上入院していることが必要です。
図解
被保険者は、入院中の食事代については、一定の負担額(食事療養標準負担額)だけを支払えば、残りは入院時食事療養費として医療保険が負担してくれます。
しかも、市区町村民税が非課税などの低所得者は、入院日数に応じて食事療養標準負担額が減額されています。
ただし、食事療養標準負担額の減額を受けるには、被保険者証をあわせて、事前に申請することで発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等窓口で提示することが必要です。
つまり、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、入院にかかる医療費と食事代が減額されるわけです。
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度) |
||
区分 |
食事療養標準負担額 | |
| ・一般(下記以外の人) | 260円 (1日3食780円) |
|
| ・低所得II 注1 ・市町村民税非課税者 |
90日までの入院 | 210円 (1日3食630円) |
| 過去12カ月で90日を超える入院 長期入院(91日目以降※)の場合 |
160円 (1日3食480円) |
|
| ・低所得I 注2 | 100円 (1日3食300円) |
|
| ・同一健保等における過去1年間の入院の日数を合算できます。合算されるのは個人単位なので、同一世帯内に他にも入院している家族がいても、その家族の入院日数を合算することは出来ません。 ・入院した場合の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として上記の標準負担額を自己負担して、残りを保険組合が負担します。 注1)70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等 注2)70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 注1・2)住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。保健組合担当窓口に申請してください。 |
||
*入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食780円を限度に1食につき260円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食1,920円を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
*食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
*被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
*なお、65歳以上74歳以下の人が療養病床に入院した場合は、「西武健康保険組合-65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき」の外部サイトに詳しいです。
*ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。具体的には、次の表のようになります。
非課税になるかの具体例(子なし夫婦の場合) |
|
*いずれも住民票上の同一世帯かどうかは問わない。
*いずれも、所得税上の扶養は関係ない。 *ここで言う「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、加入する医療保険(国保、健保など)上の世帯です。例えば、住民票上の同一世帯の夫婦が「夫は住民税非課税、妻は住民税課税」であっても、「妻が夫とは別の健康保険の保険者(健康保険組合等)の被保険者であるか、又は、夫が健康保険の被保険者で妻が国民健康保険の被保険者」であれば、夫の入院時食事療費は安くなります(=夫は住民税非課税世帯と見なします)。 *高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であれば、該当します。入院時食事療養費は、夫婦の両方が非課税所得者(奥様は健康保険の被扶養者)であれば、安い自己負担額が適用されます。 *高額療養費(低所得者)は、被保険者本人が非課税所得者であればOKですが、入院時食事療養費(安い自己負担額の適用)は、奥様が住民税を支払っていらっしゃる場合はダメです。 *患者が被扶養者の場合は、被保険者(の課税状況を)基準に見ます。自立支援に関しては、上記78で述べた通り、医療保険単位で見ます。 |
|
状況・条件(夫婦二人暮らし) |
低所得者か? |
| 夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は、夫の健保の扶養) | 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
| 夫は住民税非課税、妻は無職あるいは労働しているが低所得のため住民税は非課税(妻は国民健康保険) | 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
| 夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は夫の健保の扶養) | 高額療養費(低所得者)に該当します。妻が住民税非課税の場合のみ入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
| 夫は住民税非課税、妻は労働している(妻は自分の会社の健保) | 高額療養費(低所得者)に該当します。入院時食事療養費は、安い自己負担額が適用されます。 |
| 上記群の逆、すなわち、夫が労働していて妻が傷病手当金or障害年金生活で非課税の場合の、妻に対する医療費 | 傷病手当金を受給しているので、妻は健康保険組合等の被保険者です。妻が、住民税非課税であれば、高額療養費(低所得者)に該当します。 |
*画像で表すと以下のようになります。
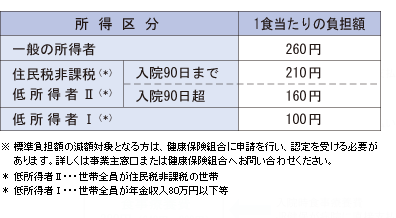
*入院時の食事にかかる費用については、療養の給付等とは別に「入院時食事療養費」として支給します。「入院時食事療養費」の額は、入院時に受けた食事にかかる費用について、患者本人が自己負担する「標準負担額(通常1食につき260円)」を控除して、残りの費用(特別食は全額自己負担)を健康保険組合が医療機関に対して直接支払うかたちで給付します。
*以前の健康保険組合等との合算は不可です。傷病手当金を退職後に貰う要件のひとつである「1年以上の加入期間」は、異なる健保組合でも合算出来る場合もありましたが、「高額療養費の多数該当」や「入院中の食事療養費」については、健康保険組合同士等の「合算の制度はありません」。