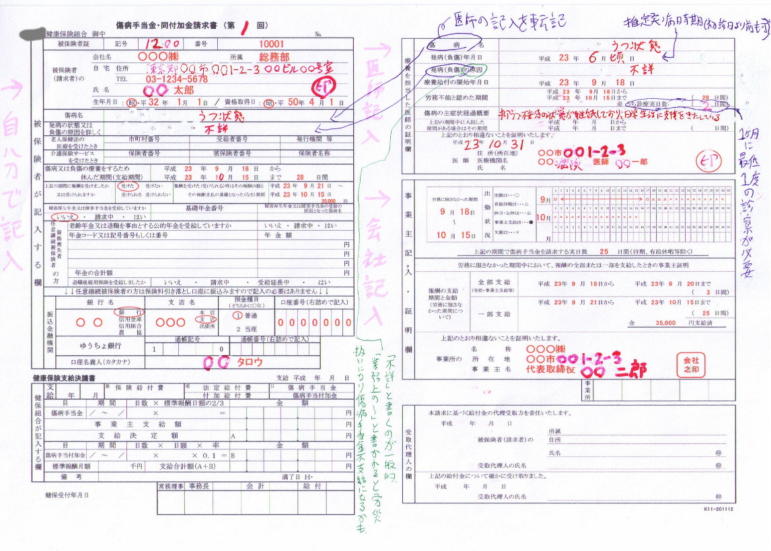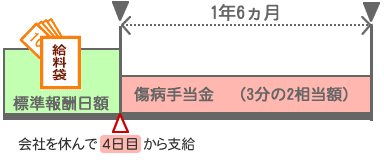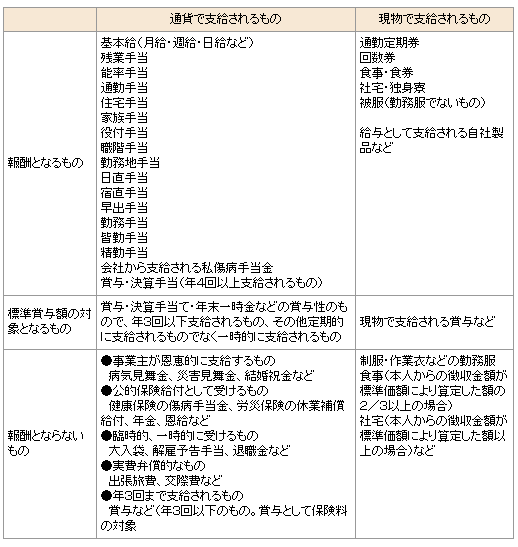傷病手当金受給要件
健康保険の被扶養者(配偶者・子供等)や、任意継続被保険者(資格喪失後の継続給付受給中の人を除く)、特例退職被保険者、国民健康保険の被保険者には支給されません。
傷病手当金支給は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法にもとづく保険者の被保険者である場合です。組合国保はその名称からわかる通り、国民健康保険法に基づく保険者です。国民健康保険法では、傷病手当金は任意給付となっており、必ず給付すべきものではありません。市町村が保険者の国民健康保険加入者には、傷病手当金の給付はありません。
また、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなるため、健康保険の傷病手当金等は支給されません。
(※)
健康保険証を持参していなければ、保険適用医療であっても自費扱いとなります。また、退職後に国民健康保険等に加入していなければ、保検適用医療でも自費扱いとなります。
ここで言う自宅療養とは、医師が診断し、私傷病により療養のため自宅療養が必要と診断された場合のことを言います。医師の診断も受けず、自宅療養していても、傷病手当金の対象とはなりません。
「美容整形手術など健康保険の対象とならないものを受けたために労務不能状態(例えば、入院が必要になった)となっても傷病手当金は支給されません。(昭和4.6.29保理1704号)」とあるように美容整形手術が失敗したから労務不能状態になったことについては何ら述べられていません。つまり、歯の矯正治療を受け労務不能状態になっても(このようなことがあるとは思えませんが)傷病手当金は支給されないという解釈です。このことから保険適用外の治療を受けても、その医療行為が失敗したため、労務不能状態となり、療養が必要と医師又は歯科医師が意見を述べ、保険者も療養のため労務不能と判断すれば、傷病手当金は支給されます。この場合「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
医師の証明が必要なので、通院または入院が必要になります。
なお、労務不能かどうかは、医師の意見を参考に、最終的には保険者が決定します。
「労務不能」であるか否かは、必ずしも医学的な基準で判断せず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に従事できるかどうかを標準として社会通念に基づいて判断します。例えば産業医と面談しても、産業医と面談した日が、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に従事出来なければ、「労務不能」となります。
傷病手当金書類は、科によらず、医師免許を有する医師であれば、誰でも記入可能です。また、研修医であっても、歯科医であっても傷病手当金申請書類は書けます。看護師が書くのは法律違反です。病院の受付の人が医師の記入ミスに気付いて訂正したりも厳密には違反です。医師に連絡し、医師の承諾の元に訂正することは可能です。
また、診察日も労務不能日に含める事ができます。具体的には、7月15日(たとえ午前中でも)の受診であっても、医師が診察し、その日が労務不能かどうか判断し、証明書に記入します(※)。
なお、傷病手当金の申請書は医師が自分の息子に対しても書けます。特に、法的規制はありません。但し、労務不能でないのに労務不能と書けば、公文書偽造となります。
(※)
医師が診断し、その日の患者の状態から判断するので、その日が労務不能の意見を書けます。なお、午前中に医師の診察を受け労務不能と判断されたが午後から出勤した場合。午前中の診断時に労務不能なくらい体調不良なのに、午後から急遽労務可能なくらい体調が回復するのも不自然な話しだと思いますが、仮に、医師がその日労務不能と意見書に記入しても、実際午後に出勤したのなら、事業主記入欄で出勤の事実を書くこととなります。申請期間にその日が含まれていても、最終的に傷病手当金の支給・不支給を決定するのは、保健康保険組合等の保険者ですので、医師が労務不能の意見を書いていても、保険者は、その日を労務不能の日とは判断せず、その日は傷病手当金は支給されません。
従って、2日休んで1日出勤し、その後再び2日休んでも、待期は完成しないので支給されません。
3日間連続で休んだ後(=4日目に)1日出勤した場合は、既に待期期間が完成しているので、その翌日(=5日目)に休んだ場合、傷病手当金が支給されます。
なお、待期期間に給与等を受けていたかどうかは関係ありません(つまり、待期期間には土曜日・日曜日・祝日・公休・調整休日・特別休日・有給休暇等を含めます。会社から休職手当が出ていても含めます)。
傷病で労務不能となり就業時間内に早退した場合は、その日から起算して3日間で待期期間は完成します。就業時間後に傷病で労務不能となった場合には、翌日から起算して3日間で待期期間は完成します。
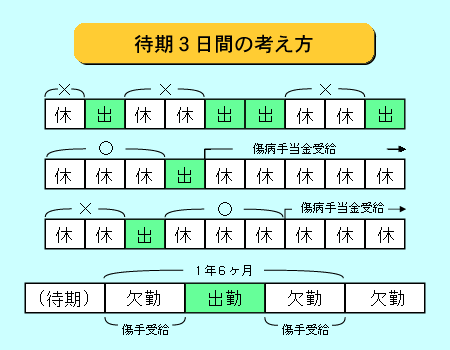
*出勤しても直ちに早退した場合は、会社が欠勤扱いし、医師も労務不能の日として証明してくれれば、傷病手当金の対象になると考えられます。少しでも就労の実態があれば、最終的には保険者が労務不能かどうかを判断し、傷病手当金の支給日になるか不支給日になるか決定します。
*本来の終業時刻が終了し、残業(超勤)中に労務不能になり退社した場合等、就業時間後私傷病で労務不能となった場合は、翌日から起算し連続する3日間の私傷病による労務不能状態があれば、待期期間は完成します。
*待期期間(労務不能期間)の合算はありません。途中で会社を変われば、そこから待期期間を計算します。たとえ、同一健保・グループ会社であってもです。
*私傷病による連続する3日間の労務不能期間のことを「待期」期間と言いますが、この3日間という期間の完成を待つという意味で「待機」ではなく「待期」という表現が用いられているのだと思慮します。
*待期期間は、必ずしも病院の営業日でなくてもかまいません。例えば、日曜日に救急搬送され通院してる病院と別の病院に搬送された場合や、地元のかかりつけの開業医は休診日だが個人的に「急に具合悪くなった、今日は休診なのは分かっているが、もし今暇なら、診てくれ」と個人的に医師の携帯電話に電話した場合などでもOKです。
*18か月以内なら、再発時には、待期期間の3日間は不要です。
*労務不能期間・待期期間は、転籍では合算不能、出向や雇用形態変化なら合算できます。
(転籍…転籍とは、出向で勤務していた勤務先に元勤務していた先を退職し、入社することをいいます。従いまして、退職を伴いますので、労務不能期間は合算出来ません。
出向…出向とは、元から勤務していた先に在籍していながら、関連会社で就労することをいいます。この場合は、退職は伴いません。通常、勤怠管理、給与の支給は元の会社で行います。出向の場合は、労務不能期間は合算されます。
同一会社で、契約社員から正社員になる…この場合も退職を伴いませんので、労務不能期間は通算されます。)
*待期期間3日間の病名と4日目以降の病名が一致することが原則です。但し、待期期間3日間の病名と因果関係がある病名でも構いません。
*以上、日勤勤務の場合を想定しています。勤務時間が2日間にまたがる場合は、2日目で早退した場合、それが残業ではなく正規の勤務時間であったとしても、その日から労務不能という扱いになります。
例)2日間にまたがる勤務とは、9時〜翌9時、16時〜翌13時など
ただし、給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。