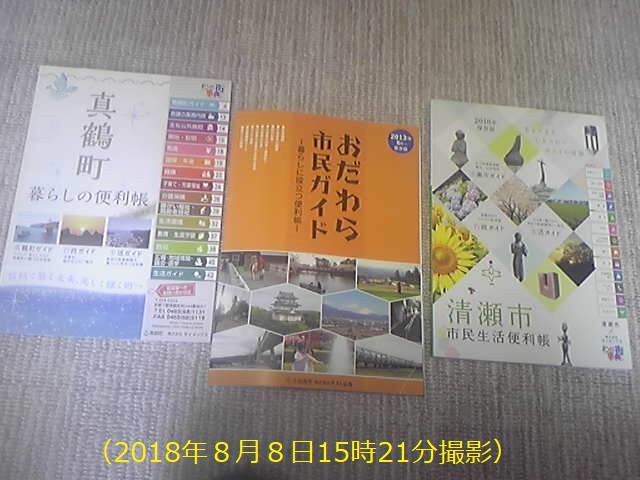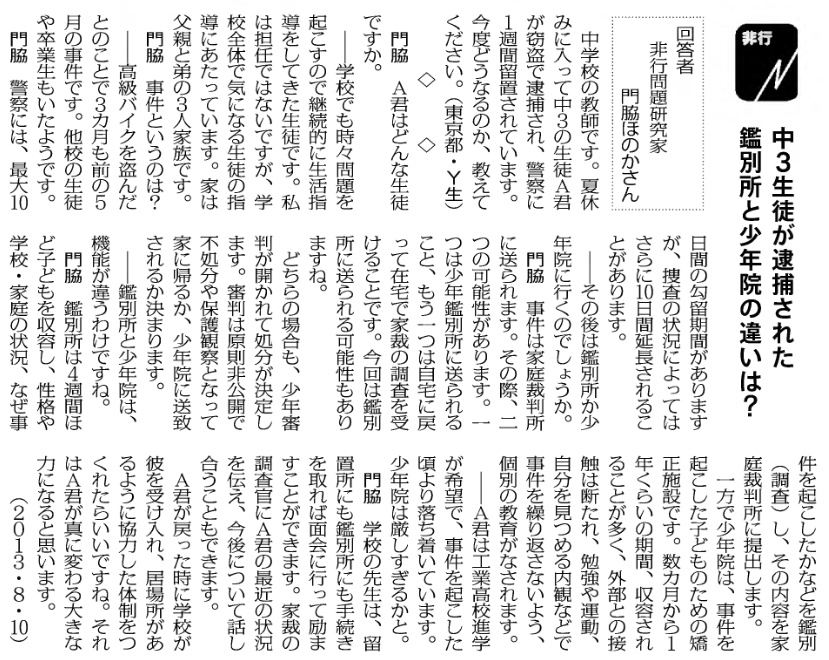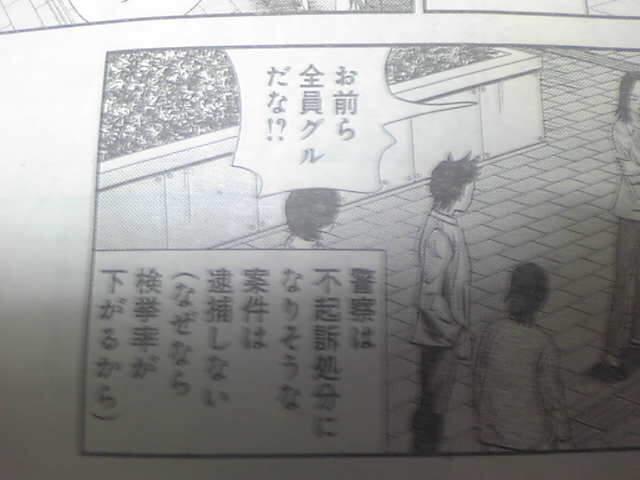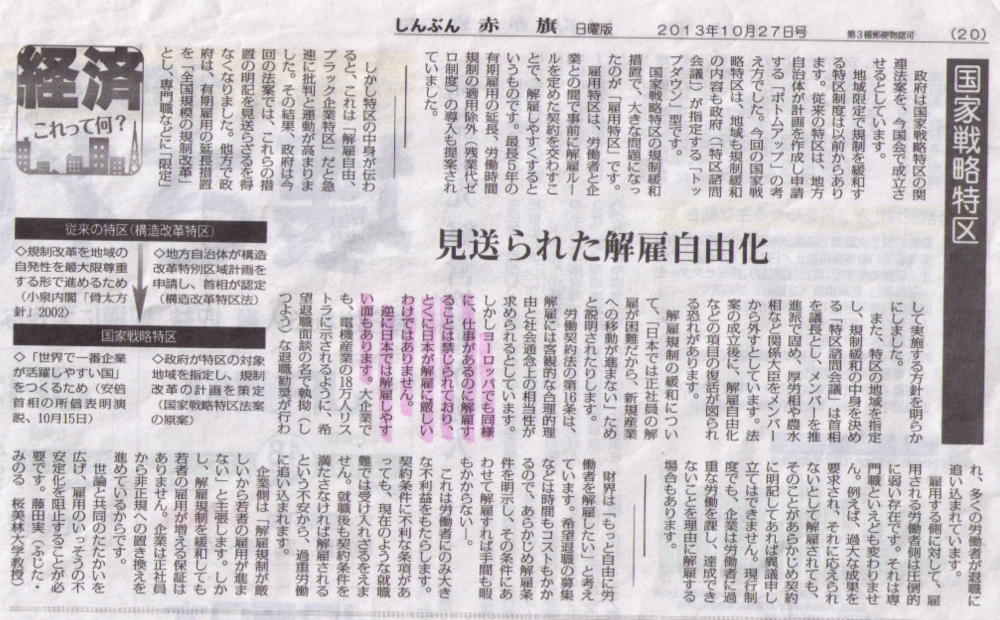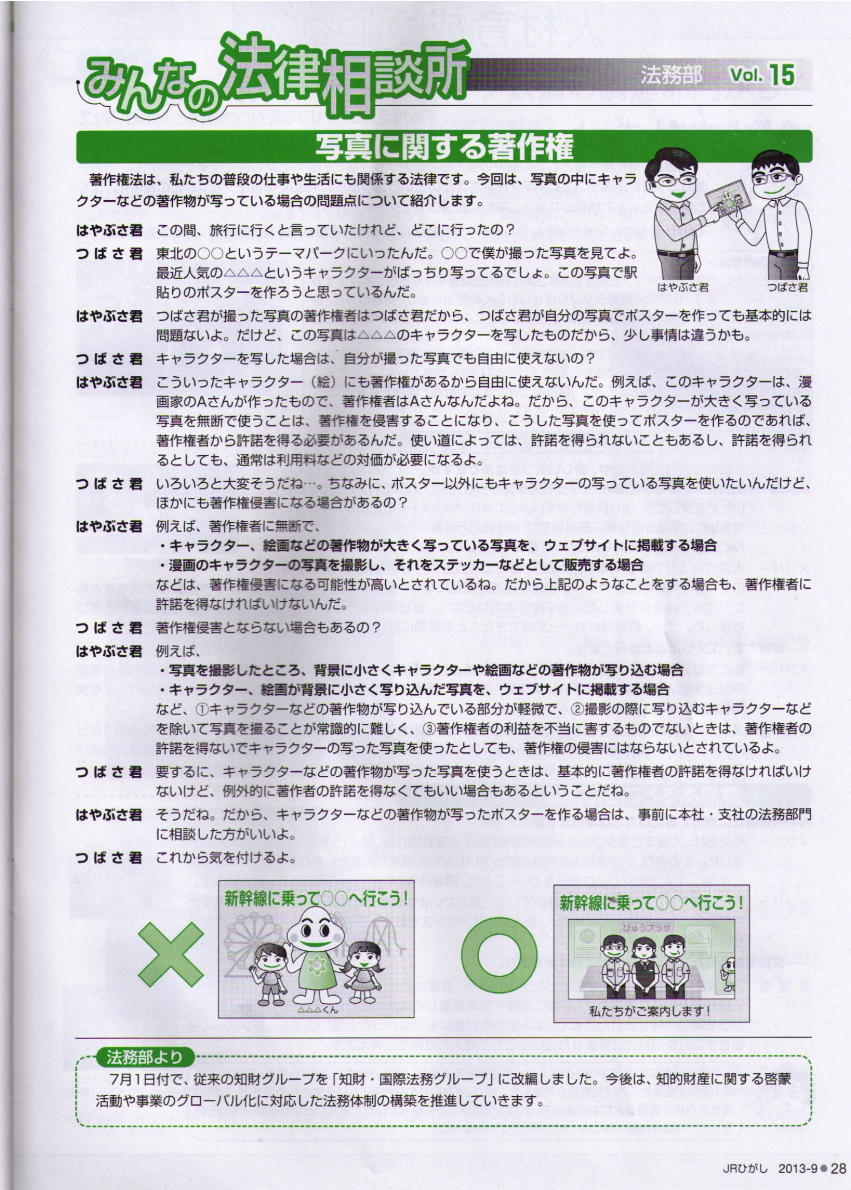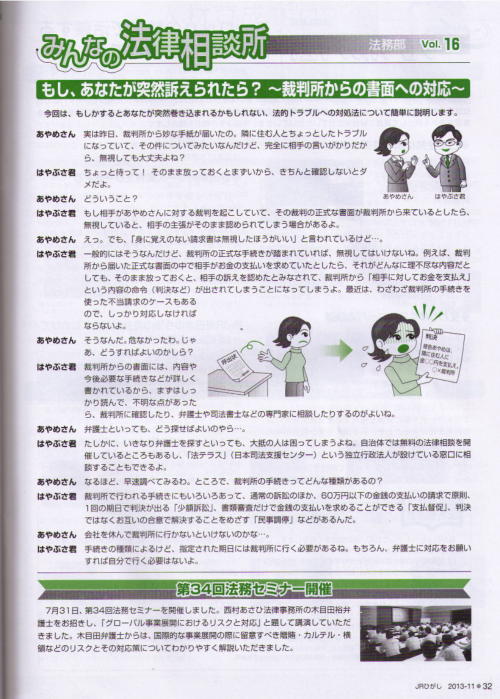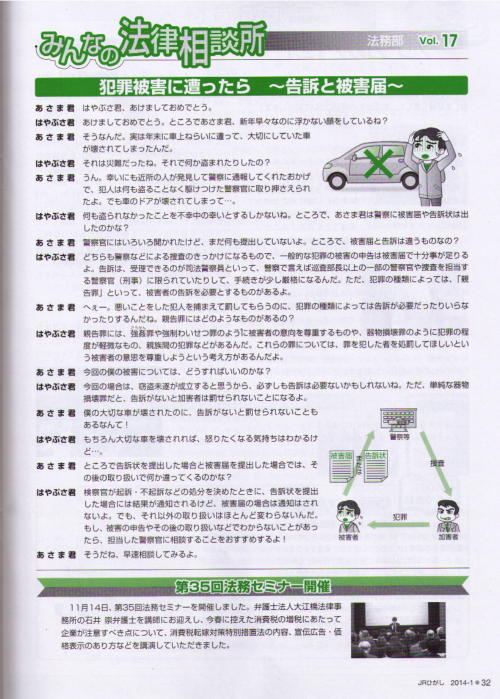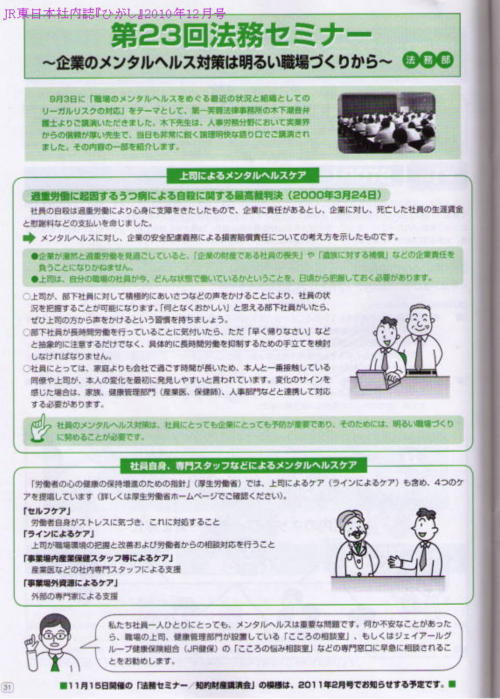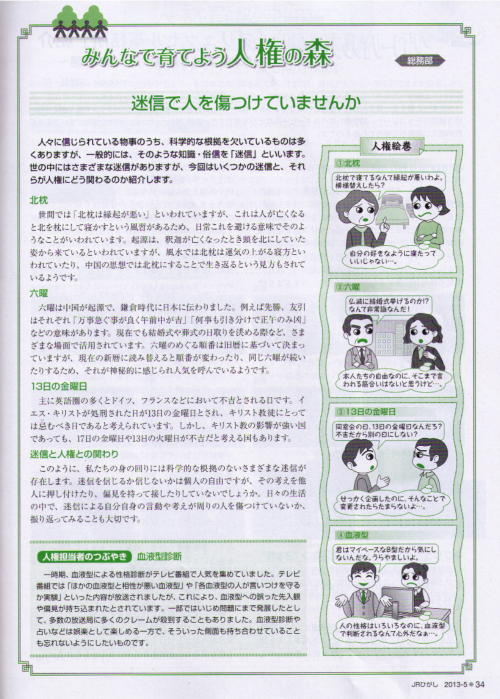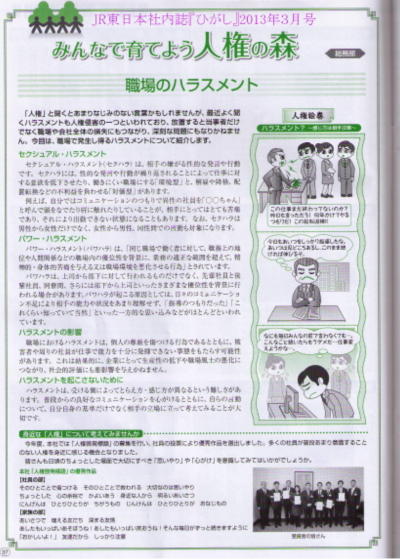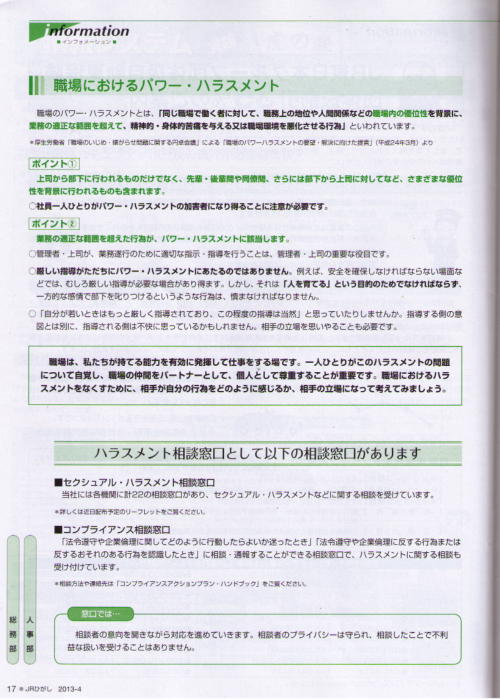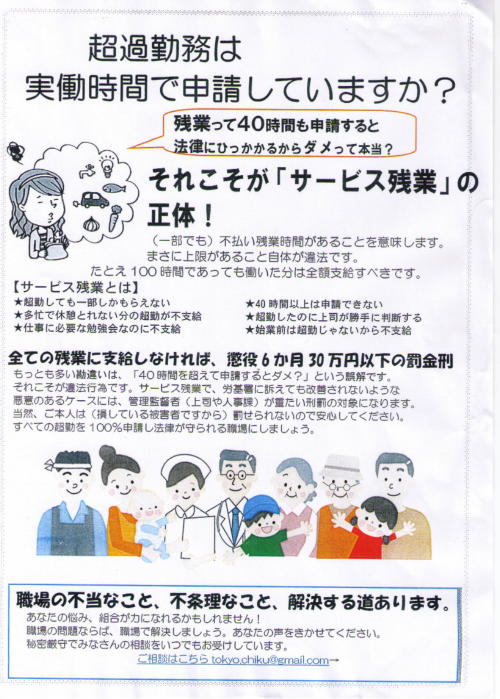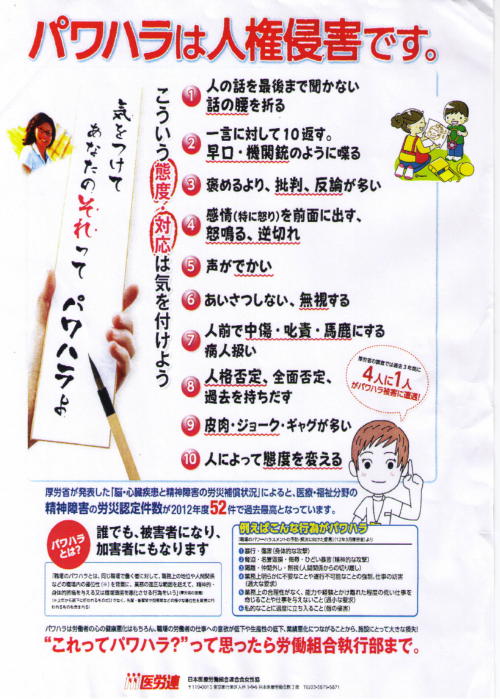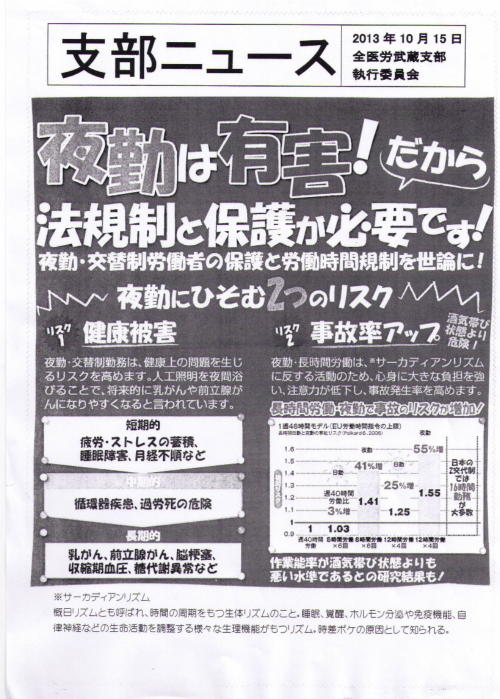�K�v�Œ���̘J���@
�����͘_�̑g�ݗ���
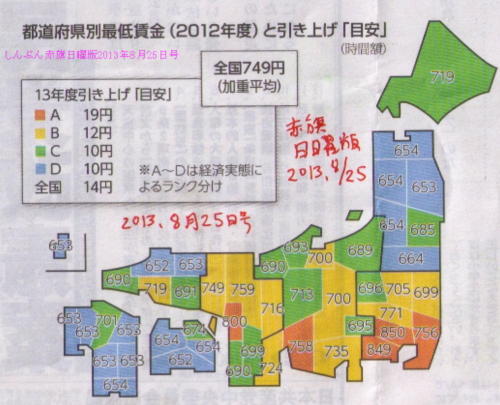
�E�Z���̃t�z��
http://�Z���[.com/?p=249
�i�i�\���@
�ٔ����b�S�_�r�����͐S�_�Վ�Ƃ͉��ł����B
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_21/index.html
| �������̘J���������킩��Ȃ��̂ł����E�E�E�i�J����@15���A���@�{�s�K��5���j |
| ���ߎn�߂�ۂɘJ���_�����킵�A�����̘J���������m���߂܂��傤�B ���g�p�҂͉��L�̓��e���A���ʂ̌�t�ɂ��J���҂ɖ�������`��������܂��B �@�J���_��̊��ԁA�A�d��������ꏊ�A�d���̓��e�A�B�n�ƥ�I�Ǝ����A�x�e���ԁA�x����x�ɁA�A�Ǝ��]���i����E�V�t�g���̋Ζ������j�C�����̌��ߕ��A�v�Z���@�A�x�����@�A�����̒��ؓ���x�����A�D�ސE�Ɋւ��邱�Ɓi���ق̎���Ɨ��R���܂ށj�A�E���ԊO�J���̗L�� ���J����@����߂�J�������͍Œ��ł��̂ŁA�@���̊�ɒB���Ȃ��J���_��̕����́A�@���̊���K�p����܂��B |
| ���A�ƋK�����������Ƃ�����܂���B�i�J����@89�`93��106�𤓯�@�{�s�K��49��1���52����2�A�J���_��@7���j |
| ���J���ҁi�p�[�g��_��Ј����܂ށj���펞10�l�ȏア�鎖�Ə�ł́A�A�ƋK�����쐬���A�J���҂̉ߔ������\����҂̈ӌ�����Y���āA�J����ē��ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�܂���B�A�ƋK����ύX����Ƃ����A���l�̎葱�����K�v�ł��B ���A�ƋK���͏펞���₷���ꏊ�Ɍf������ȂǁA�J���҂Ɏ��m���Ȃ���Ȃ�܂���B |
| �������i�����j�E�J�����Ԃō����Ă��܂��B�i�J����@11��12��24���`28�𤓯�@�{�s�K��7����2�8��9��Œ�����@�j |
| �������i�����j�� �������̎x�����ɂ͖@���Œ�߂�ꂽ����5�̊�{����������܂��B �@�ʉ݂Łi�@�߂�J������ŕʂɒ�߂�����ꍇ�������܂��j�A�A���ځA�B�S�z�i���Q����������Ɉ����܂���B�ŋ���Љ�ی�����J�g����Ō��߂Ă�����̂������܂��j�A�C����1��ȏ�A�D�������̎x�� �i�ܗ^�ȂǗՎ��̂��̂������܂��j �������Ƃ��ĒN�ł��A�Œ�����z�ȏ�̒������x������K�v������܂��B�i���p���Ԓ��Ȃǂ͘J���ǒ��̋��ɂ��K�p���O�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B�j ���g�p�҂̓s���ɂ��x�Ƃ͕��ϒ�����6���ȏ�̋x�Ǝ蓖���x�����Ȃ���Ȃ�܂���B �����������͏A�ƋK���ɒ�߂��Ȃ���Ώo�����A�@1��̊z�����ϒ�����1������2����1�A�A���z��1�����x�����ɂ�����������z��10����1�A���邱�Ƃ͂ł��܂���B ����Ђ��|�Y�������ߒ������������ɂȂ������A������Ђɑ����āu�����������̑��z��8���v�i�N��ɂ�����z���قȂ�܂��j�𗧑֕������鐧�x������܂��B ���J�����ԁ� ���g�p�҂́A�@��J�����ԁi1�T40���ԁA1��8���ԁi��O����j�j����J�����ԂɁA���������i���ԊO�J����2��5�����A�[��J���i22���`5���j��2��5�����A�x���J����3��5�����j���x����Ȃ���Ȃ�܂���B�Ȃ��A��60���Ԃ��z���鎞�ԊO�̘J���ɂ́A5�����ȏ�̊����������x�������A�J�g����ɂ��L���̑�x�ɂ�t�^���邱�Ƃ��K�v�ł��i�����̊ԁA���Ƃ݂̂ɓK�p�ƂȂ��Ă��܂��j�B |
| ���J���҂͒N�ł��N���L�x�x�ɂ��Ƃ����Ė{���H�i�J����@39��136�𤓯�@�{�s�K��24����3�j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���ߎn�߂�������6���������ċΖ����A����J��������8���ȏ�o���Ă���A�g�p�҂͔N���L���x�ɂ�^���Ȃ���Ȃ�܂���B ���p�[�g�^�C�}�[�ȂǏT�̏���J�����Ԃ��Z���J���҂ɂ��A�g�p�҂͘J�������ɉ����ĔN���L���x�ɂ�^���Ȃ���Ȃ�܂���B ���N���L���x�ɂ̐����͑O�����Ă��Ȃ���Ȃ�܂��A�g�p�҂͐��������ނ��Ƃ͂ł����A���Ƃ̐���ȉ^�c��W����ꍇ�̂ݎ��G��ύX���邱�Ƃ��ł��邾���ł��B ���J�g��������ׂA1�N��5���ȓ��͈̔͂ɂ����Ď��ԒP�ʂ̔N���L���x�ɂ��擾�ł��܂��B
�����F�T�̘J�����Ԃ�30���Ԉȏ�̏ꍇ�́A�T5���ȏ�̘J���҂Ɠ��l�̈����ɂȂ�܂��B ���ސE�\��҂ɑ��Ďg�p�҂͎����ύX�����s�g�o���܂���B�ސE�\��҂ɑސE��ɔN�x��t�^���鎖�͏o���Ȃ����߂ł���A�ސE�\��҂���N�x�����̐\���o���������ꍇ�́A�Ɩ��Ɏx����������ꍇ�ł����Ă����z�̔N�x��^���Ȃ���Ȃ�܂����B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���ސE�������̂ł����E�E�E�i���@627��628��J����@89���j |
| ���_����Ԃ̒�߂̂Ȃ��J���҂́A�J���҂������̓s���Ŏg�p�҂ɐ\���o��Ό_��r���Ŏ��߂邱�Ƃ��ł��A���@�ł͑ސE��\���o��������2�T�Ԃ��o�߂���Ǝg�p�҂̏������Ȃ��Ă��ސE�������ƂƂȂ�܂��B�������A�A�ƋK�����ŕʂɊ��Ԃ��߂��ꍇ�́A����ɂ���������悢�ꍇ������܂��B ���L���_��J���҂́A�J���҂ɏA�J���p���ł��Ȃ����R������ΑސE�͉\�ł����A����ȊO�͑ސE�ɍۂ��đ��Q���������߂��邱�Ƃ����蒍�ӂ��K�v�ł��B������1�N�ȏ�̌_��̏ꍇ�͋ߎn�߂�������1�N������͎g�p�҂ւ̐\���o�ɂ�肢�ł����߂��܂��B ���N���L���x�ɂ̎擾�́A�ސE���܂łƂȂ�܂��B ��������̘J���҂��A�ސE�̎Љ�I���[���i�@�ސE�̈ӎv����i�ɓ`���A���ʂœ͂���B�A�d���̈��p��������B�j����邱�Ƃ����߂��܂��B |
| ���ސE�����Ƃ��̎葱���i�J����@115��ٗp�ی��@�{�s�K��16�𤏊���Ŗ@226���j |
| ���ސE���́A�A�ƋK���Ȃǂɒ�߂�����Ύ��܂��B �������́A�ސE����5�N�ԁA������������2�N�ԂŁA���������Ȃ��Ȃ�̂Œ��ӂ��K�v�ł��B ���g�p�҂́A�@���E�[�i�ٗp�ی��̎��Ƌ��t�����邽�߁j�A�A�ٗp�ی���ی��ҏA�B�����[�i�J���҂��N�̓r���őސE�����ꍇ�B�ސE���Ȍ�1�����ȓ��j�s���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�N���蒠�̎�̂��K�v�ł��B |
| �����ق��ꂻ���ł��B�i�J���_��@16��17��J����@3��19�`22��38����4�104��J���g���@7��j���ٗp�@��ϓ��@9��17��2����玙�E���x�Ɩ@10��16��16����4��h���@49����3��ʘJ���W�����������i�@4��3������v�ʕ�ҕی�@3�𤖯�@90��628���j |
| �����ق́A�g�p�҂̈ӎv�ŘJ���_�������I�ɏI�������邱�Ƃ������A���ٗ��R�Ɖ��َ葱�̓_�� �̍��@�����K�v�ł��B �����ٗ��R�ɂ��ẮA�u���ق́A�q�ϓI�ɍ����I�ȗ��R�������A�Љ�ʔO�㑊���ł���ƔF�߂��Ȃ��ꍇ�́A���̌����𗔗p���悤�������̂Ƃ��āA�����ɂ���B�v�ƒ�߂��Ă��܂��B�i�J���_��@16���j �����̉��ق͖@���ŋ֎~����Ă��܂��B�@�Ɩ���̍ЊQ�ŋx�ƒ��̊��ԂƂ��̌��30���ԁA�A�Y�O�Y��x�ƒ��̊��ԂƂ��̌��30���ԁA�B������D�P��o�Y��玙����x�Ƃ𗝗R�Ƃ�����̓������َ葱�ɂ��ẮA30���ȏ�O�ɉ��ق�\�����邩�A30�����ȏ�̕��ϒ����i�u���ٗ\���蓖�v�j���x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���߂��Ă��܂��B���p���Ԓ��̘J���҂ł����Ă�14�����Čٗp���ꂽ�ꍇ�́A�\���̎葱���K�v�ł��B�i�J����@20���j�����Ԃ��߂��J���_��́A��ނȂ����R������ꍇ�łȂ���Ό_����Ԃ���������܂ʼn��قł��܂���B�J���_�r���ʼn������ꂽ�Ƃ��A�J���҂ɏd��ȉߎ�������ꍇ�������āA�J���҂͎g�p�҂ɑ��c��̌_����Ԃɑ�����s���s�̑��Q�����𐿋����邱�Ƃ��ł��܂��B ���o�c�s�U�Ȃǂ𗝗R�Ƃ���l�������̂��߂̉��فi�u�������فv�j�ł��A����4�̗v�����[�����Ȃ���A���قł��܂���B ���@�l���팸�ɏ\���ȕK�v��������A�A���ق��������w�͋`�����\���s�������A �B���ّΏێ҂̑I�ѕ��������E�Ó��ł���A�C�����E���c�葱��s�����Ă��� ���L���J���_��i�L���J���_��3��ȏ�X�V����Ă��邩�A1�N���Čp�����Čٗp����Ă���J���҂Ɍ���j���X�V���Ȃ��ꍇ�i������u�َ~�߁v�j�A���Ȃ��Ƃ��_����Ԃ���������30���O�܂łɁA���̗\��������K�v������܂��B ���h���悩��h���_��𒆓r���Ă��A�h�����Ƃ̌ٗp�W�����R�ɏI�����܂���̂ŁA�c��̌ٗp���Ԃɑ��Ă̒����𐿋��ł��܂��B |
| ���J���ی��E�Љ�ی��ɉ����ł��܂����H(�ٗp�ی��@��J�Еی��@����N�ی��@������N���@) | ||||||||||||||||||
| ���J���ی��ƎЉ�ی��̉�����͈ȉ��̂Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B �i�K�p����Ȃ����Ə�������܂��̂ŁA�ڂ����͂��⍇���������B�j
|
||||||||||||||||||
�����͘_�̑g�ݗ���
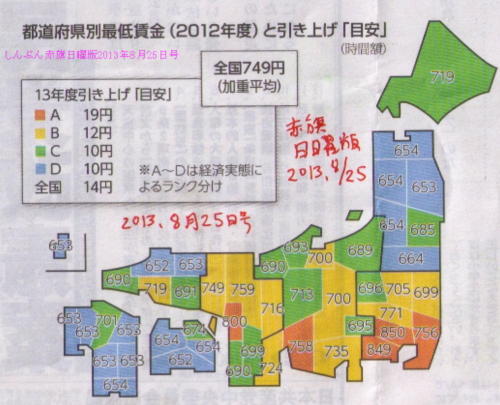
�E�Z���̃t�z��
http://�Z���[.com/?p=249
�i�i�\���@
�ٔ����b�S�_�r�����͐S�_�Վ�Ƃ͉��ł����B
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_21/index.html
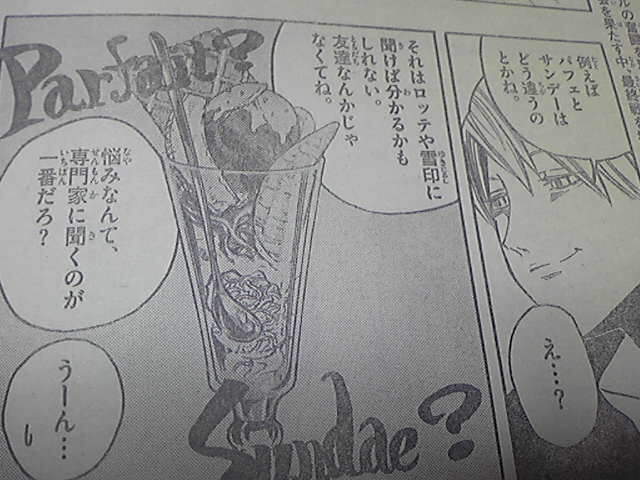

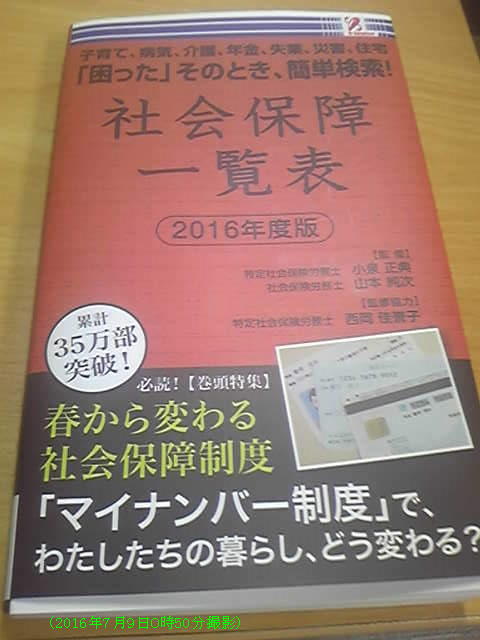 �@
�@